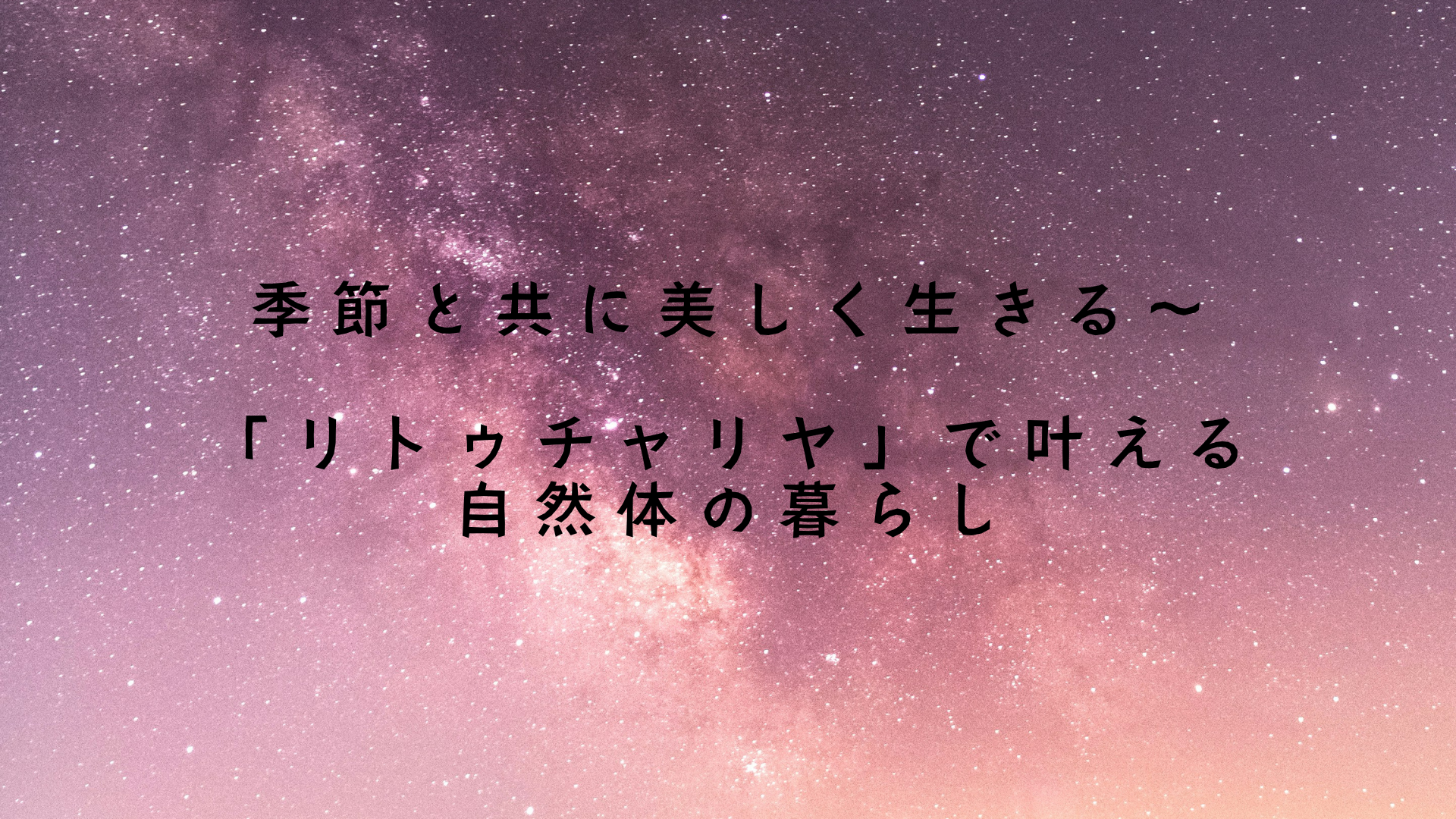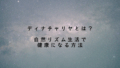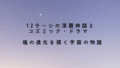5000年以上も受け継がれてきたヴェーダの叡智は、季節との向き合い方について提案をしてくれています。それが「リトゥチャリヤ(Ritucharya)」—自然のリズムと調和して生きる、古代からの贈り物です。
リトゥチャリヤとは?—季節と共に歩む美しい生き方
リトゥチャリヤは「リトゥ(季節)」と「チャリヤ(生活法)」を組み合わせた言葉で、アーユルヴェーダの中核をなす考え方です。一年中同じルーティンを繰り返すのではなく、食事、睡眠、運動、そして心の在り方まで—すべてを季節の特性に合わせて調整していく智慧なのです。
考えてみてください。桜咲く春の軽やかさと、雪景色の静寂な冬。あなたの心と体は、本当に同じものを求めているでしょうか?自然が教えてくれる美しいリズムに耳を傾けてみませんか。
日本の四季に寄り添う六つの季節
ヴェーダの伝統では、一年を六つの季節に分けて捉えます。日本の気候に合わせて、その智慧を現代の私たちの暮らしに活かしてみましょう。
ヴァサンタ(春)- 3月〜5月
キーワード:浄化と新生
桜のつぼみが膨らみ始める頃、私たちの体も冬の間に蓄積されたものを手放そうとしています。重く滞りがちなカパ(水・土の要素)が優勢になるこの季節は、心も体も軽やかにすることが大切です。
山菜の苦味やタケノコの力を借りて、自然なデトックスを。温かく消化の良い食事で、内側から春の光を取り込みましょう。新しいことを始めるのにも最適な季節です。

2. グリーシュマ(夏)- 6月〜8月
キーワード:冷却と調和
太陽の恵みが溢れるこの季節は、同時にピッタ(火の要素)が高まる時期でもあります。体を内側から冷やす食材—きゅうり、スイカ、ミントなどを上手に取り入れて。
早朝の清々しい時間を大切にし、日中は無理をせず、夕涼みを楽しむ。昔ながらの日本の暮らしの智慧と、とても似ていませんか?

3. ヴァルシャー(雨季)- 梅雨時期
キーワード:消化力の養生
湿度が高く、なんとなく体が重だるく感じられる梅雨の季節。消化力が弱くなりがちなこの時期は、温かく消化に優しい食事を心がけて。
生ものや冷たいものは控えめにし、スパイスの力を借りて体の巡りを良くしましょう。しょうがやシナモンが特におすすめです。

シャラッド(秋)- 9月〜11月
キーワード:収穫と感謝
実りの季節、秋。まだ夏の熱が体に残っているため、引き続き体を冷ます食材を取り入れながら、徐々に温める食材も加えていきます。
お月見の夜には月光浴を楽しみ、心身の調和を図って。季節の恵みに感謝の気持ちを込めて、丁寧に食事をいただきましょう。

ヘマンタ(初冬)- 11月〜12月
キーワード:蓄積と滋養
消化力が最も強くなる季節です。根菜類や温かいスープで体を内側から温め、冬に向けて体力を蓄えていきます。
早めの就寝を心がけ、キャンドルの灯りでゆったりとした夜時間を過ごすのも素敵ですね。

シシラ(厳冬)- 1月〜2月
キーワード:静養と内省
一年で最も静かな季節。ヴァータ(風・空の要素)が優勢になり、乾燥しやすくなります。オイルマッサージや温かいお風呂で体を労わり、十分な睡眠を。
読書や瞑想など、内面を豊かにする時間を大切にしましょう。春への準備を静かに整える、美しい季節です。

今日から始める、季節美容と健康法
春の美しさを育む習慣
- 朝のレモン白湯:デトックス効果で肌の透明感をアップ
- ドライブラッシング:リンパの流れを良くして、むくみを解消
- 軽やかな運動:ヨガやウォーキングで冬の重さを手放して
夏の輝きを保つ秘訣
- ローズウォーター:肌を鎮静させ、内側から涼やかに
- 朝フルーツ:酵素の力で消化をサポート
- 月光浴:夜の静けさで心を整えて
秋の豊かさを味わう方法
- 温かいスパイスティー:シナモンやカルダモンで体を温め始める
- 温感マッサージ:手のひらで顔を包むように温めながらマッサージ
- 感謝の時間:一日の終わりに小さな幸せを数えて
冬の静寂を楽しむコツ
- アーユルヴェーダオイル:セサミオイルやアーモンドオイルで全身マッサージ
- 温活習慣:湯たんぽや腹巻きで体の芯から温めて
- キャンドル瞑想:炎のゆらぎで心を静めて
自然と共に、もっと美しく
リトゥチャリヤの本質は、「自然のリズムに寄り添って、自分らしく美しく生きる」ことです。季節という大きな波に逆らうのではなく、その波の上を優雅に舞うように。
春には春の軽やかさを、夏には夏の情熱を、秋には秋の深みを、そして冬には冬の静けさを。それぞれの季節の美しさを、心から味わってみませんか?